【第1回】新生児期〜1歳半:最初の違和感
わが家の息子は、現在4歳でASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けています。
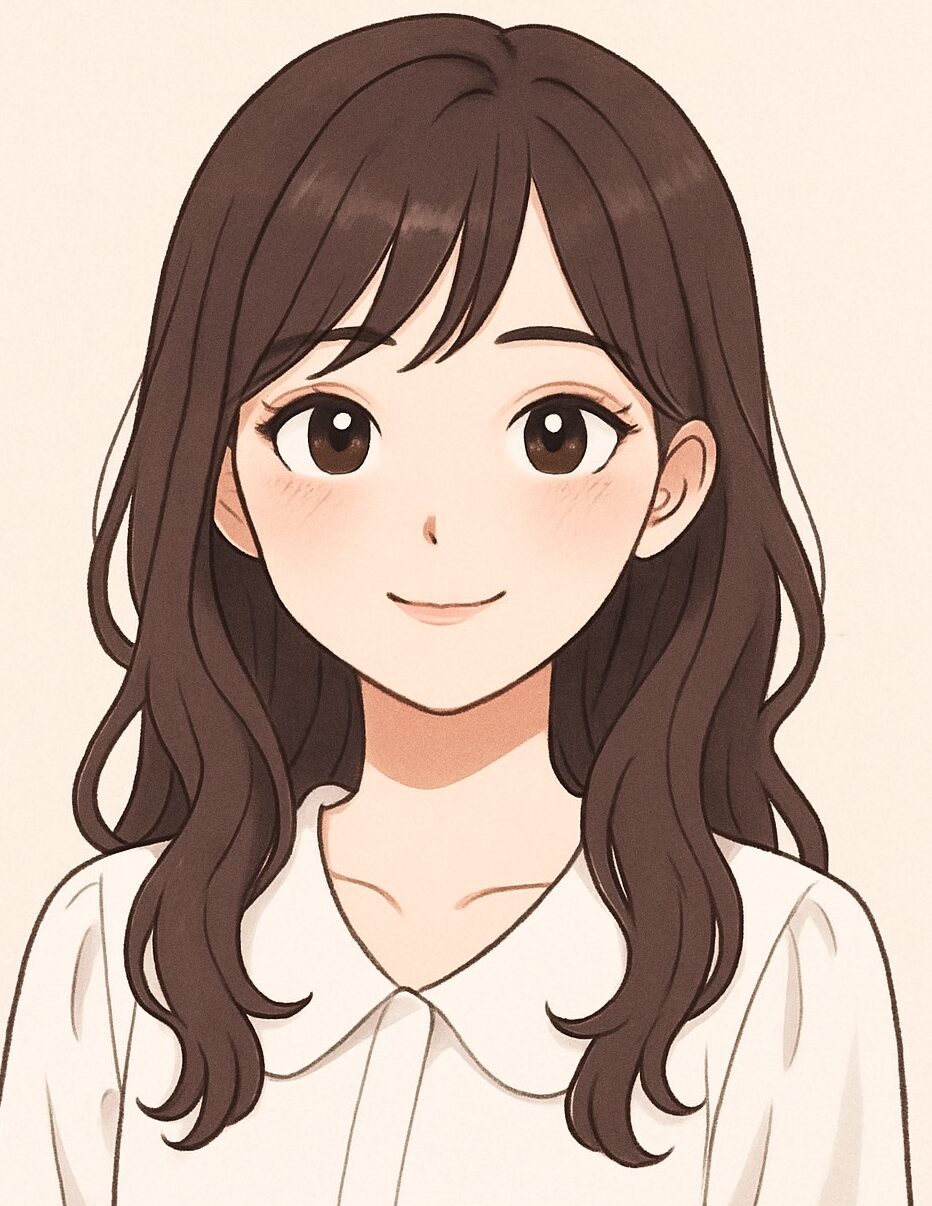
今回から数回に分けて、息子がASDと診断されるまでのことを振り返って書いてみようと思います。
はじめに ― このシリーズを書く理由
息子がASDと診断されてから半年が経ちました。
生まれてからの3年半、ずっと「これは定型かな?それとも発達障害?」と揺れ動く日々を過ごしてきました。
この気持ちを、今まさに同じように不安を抱えている誰かに届けたいと思ってブログを始めました。
かつての私のように悩んでいるお母さんは多いと思います。
「うちの子に限って違うよね」
「ここはできるけど、ここはなかなか進まない」
夜中にスマホで検索して余計に不安になること、きっと誰にでもありますよね。
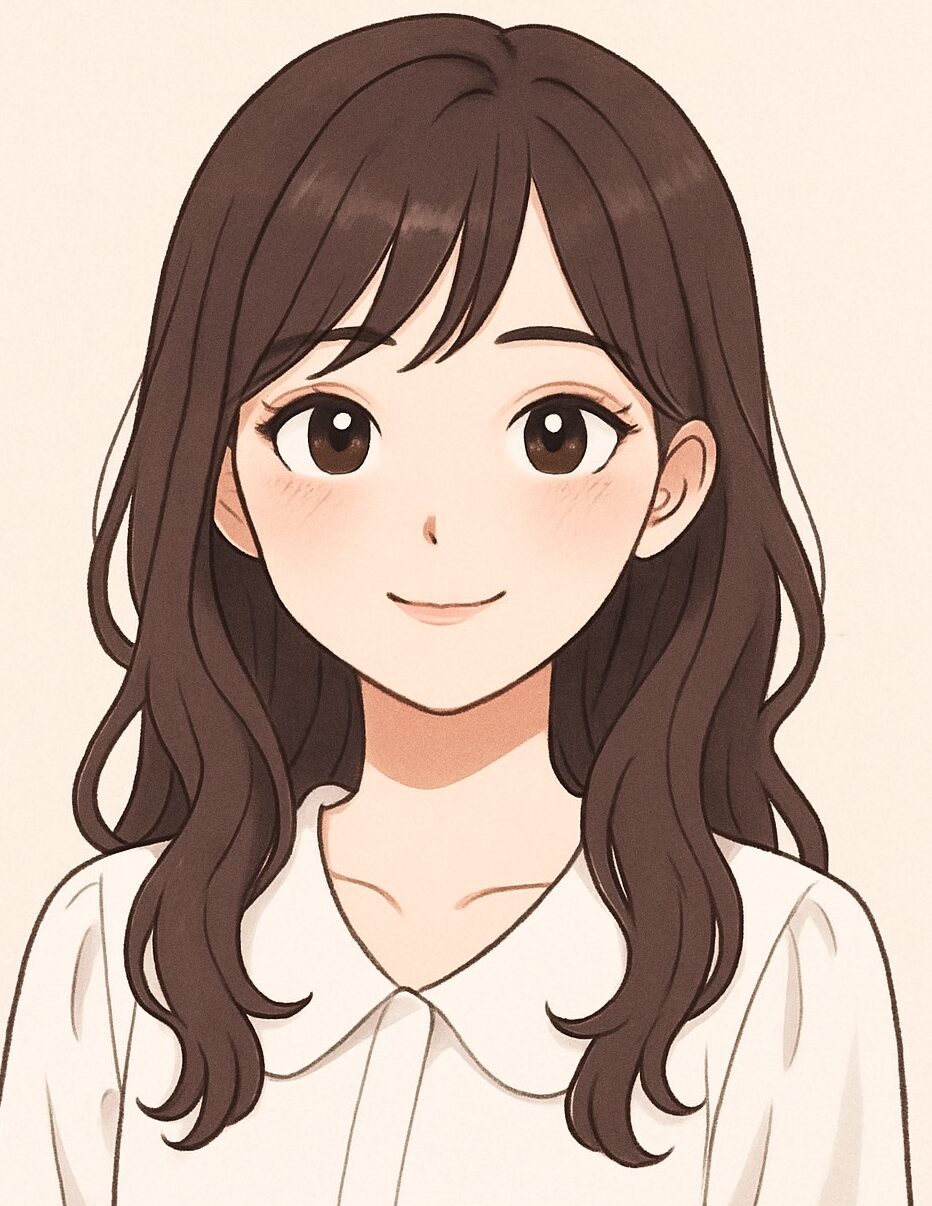
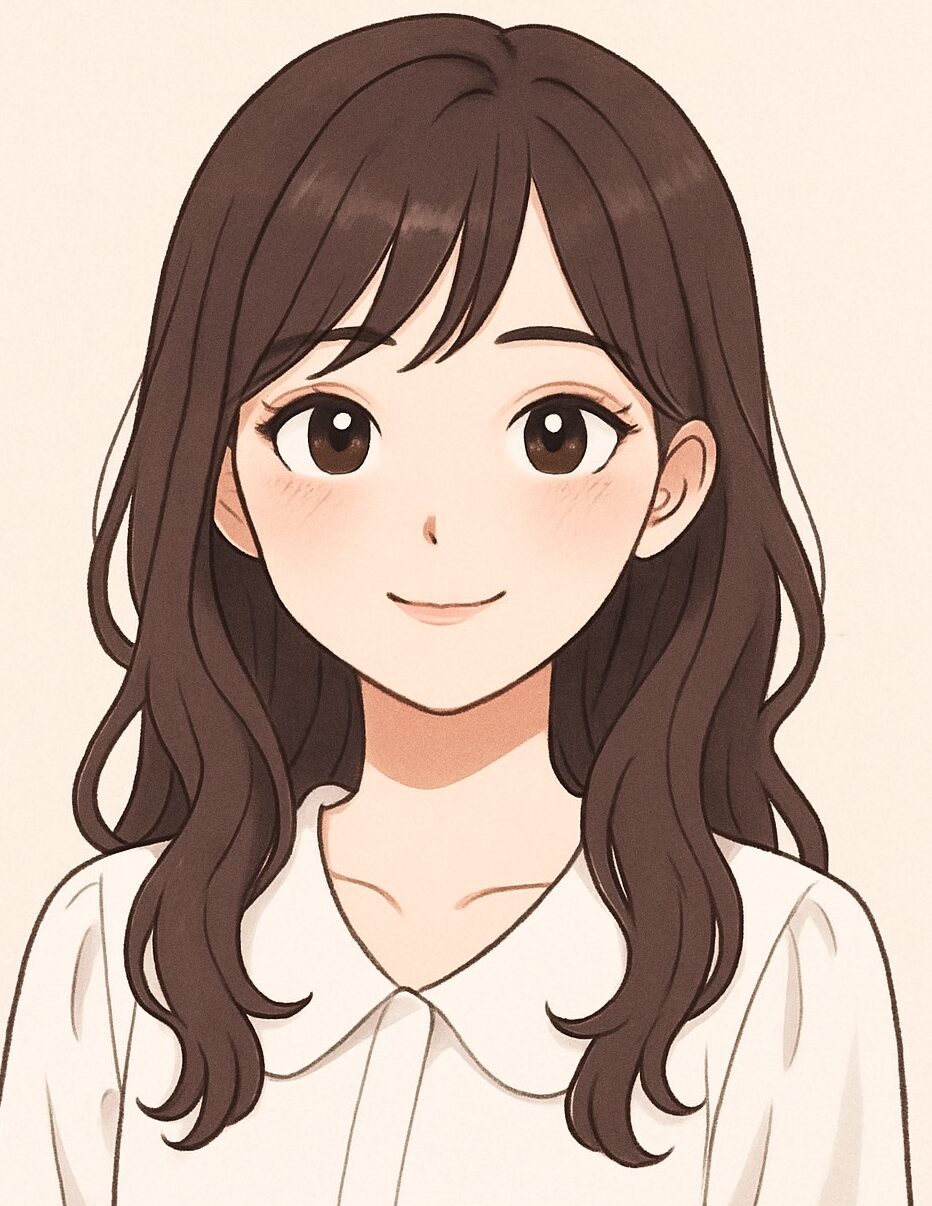
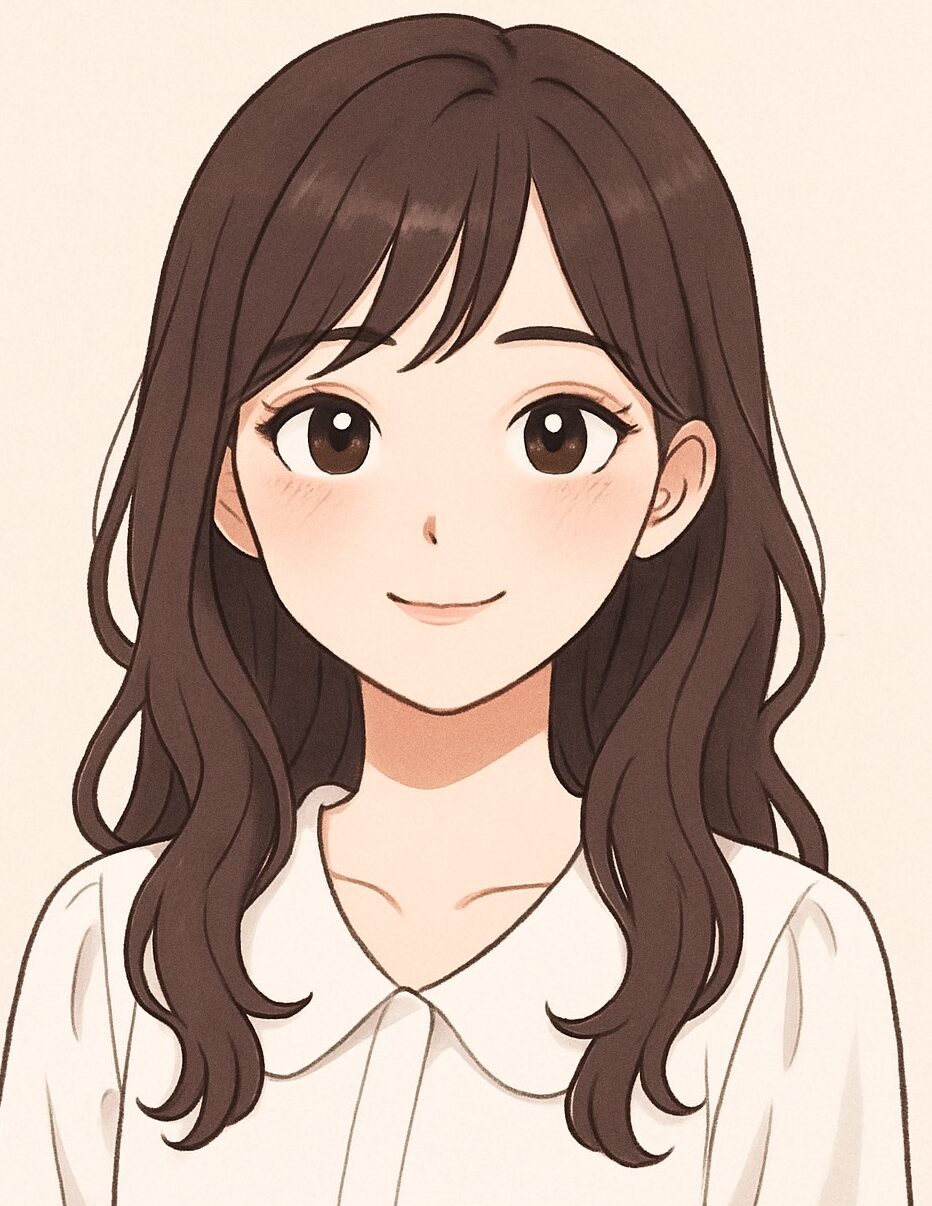
だからこそ大切にしたいのは「うちの子の幸せ」
発達障害でも定型発達でも、幸せの本質は変わらないことを伝えたいです。
抱っこしか許されなかった新生児期
今思えば、息子なりの「こだわり」はこの頃からありました。
抱っこは私以外拒否。パパも、おじいちゃんおばあちゃんも、病院の先生や看護師さんたちもダメ。
まだ首も座っていないのに、そり返る勢いで永遠に泣き続けていました。
「なんで私じゃないとだめなの?」
「私、間違ってる?育て方悪い?」
そんなふうに思っていたのを、今でもはっきり覚えています。
1分も降ろすことの許されない生活。24時間ほぼフルで抱っこ。
夜中、私は座って息子を抱っこしたまま眠っていました。
「こんなに泣く赤ちゃん、他にいるのかな?」
「これって普通?それとも…?」
誰にも聞けず、誰にも会えず。
ただただ、“生きること”だけを考えていた、そんな赤ちゃん期の始まりでした。
生後3か月まで続いた「24時間抱っこ生活」
生後3ヶ月ごろまで、本当にずっと抱っこの毎日でした。
ただ、救いだったのはたまたま試したコニー抱っこ紐が息子にぴったり合っていたこと。
新生児用のインサートに入れてあげると、すーっと安心したように眠ってくれたのです。
それまで1分も降ろせない日々だったので、この変化は私にとってまさに“奇跡”でした。
当時はコロナ禍真っ只中。誰にも頼れず、比べる相手もいなかったから、
「赤ちゃんってこういうものなんだ」と思っていました。
だから、掃除も洗濯も夫の食事作りも、新婚時代と変わらないくらいこなしていたと思います。
その反動なのか、この頃の記憶は本当にびっくりするほど残っていません。
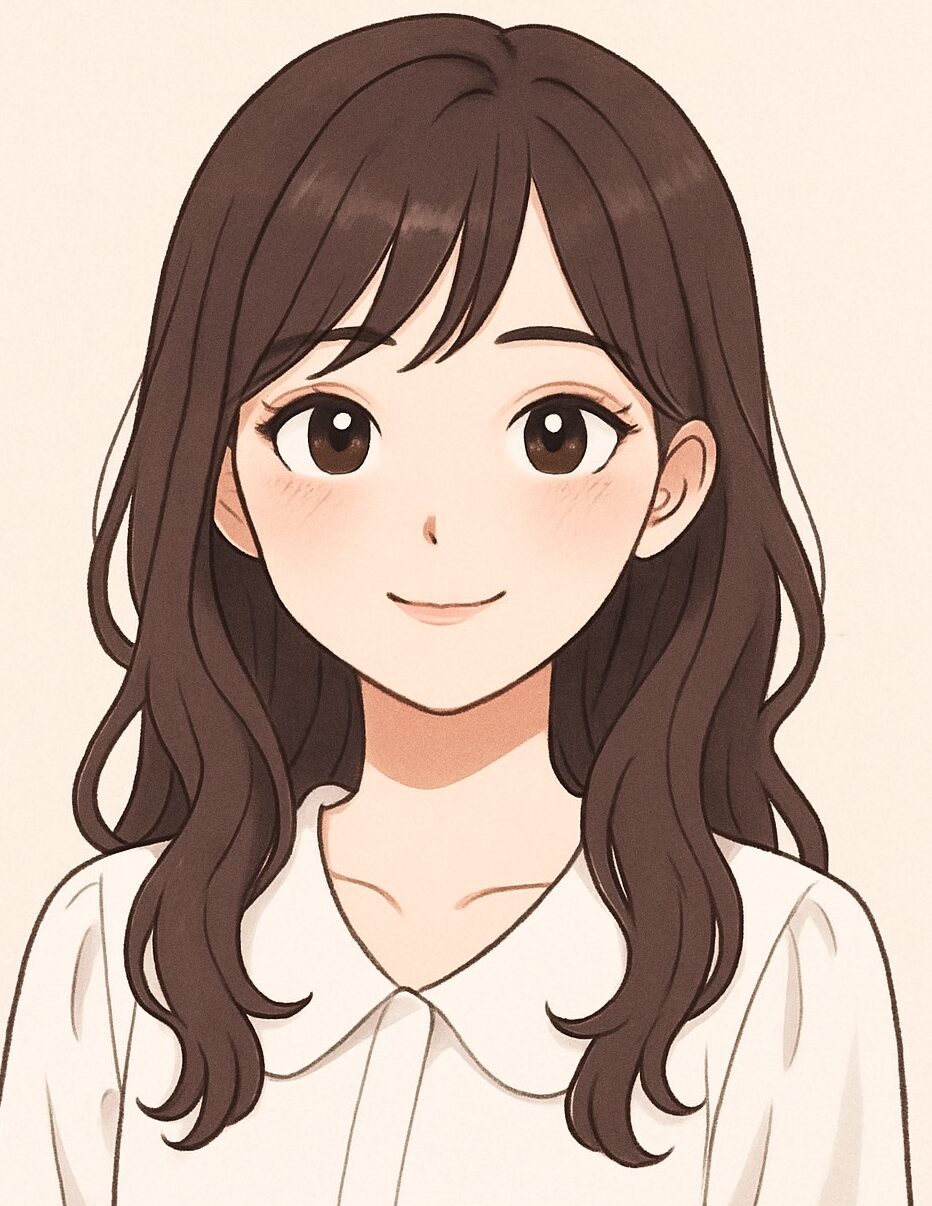
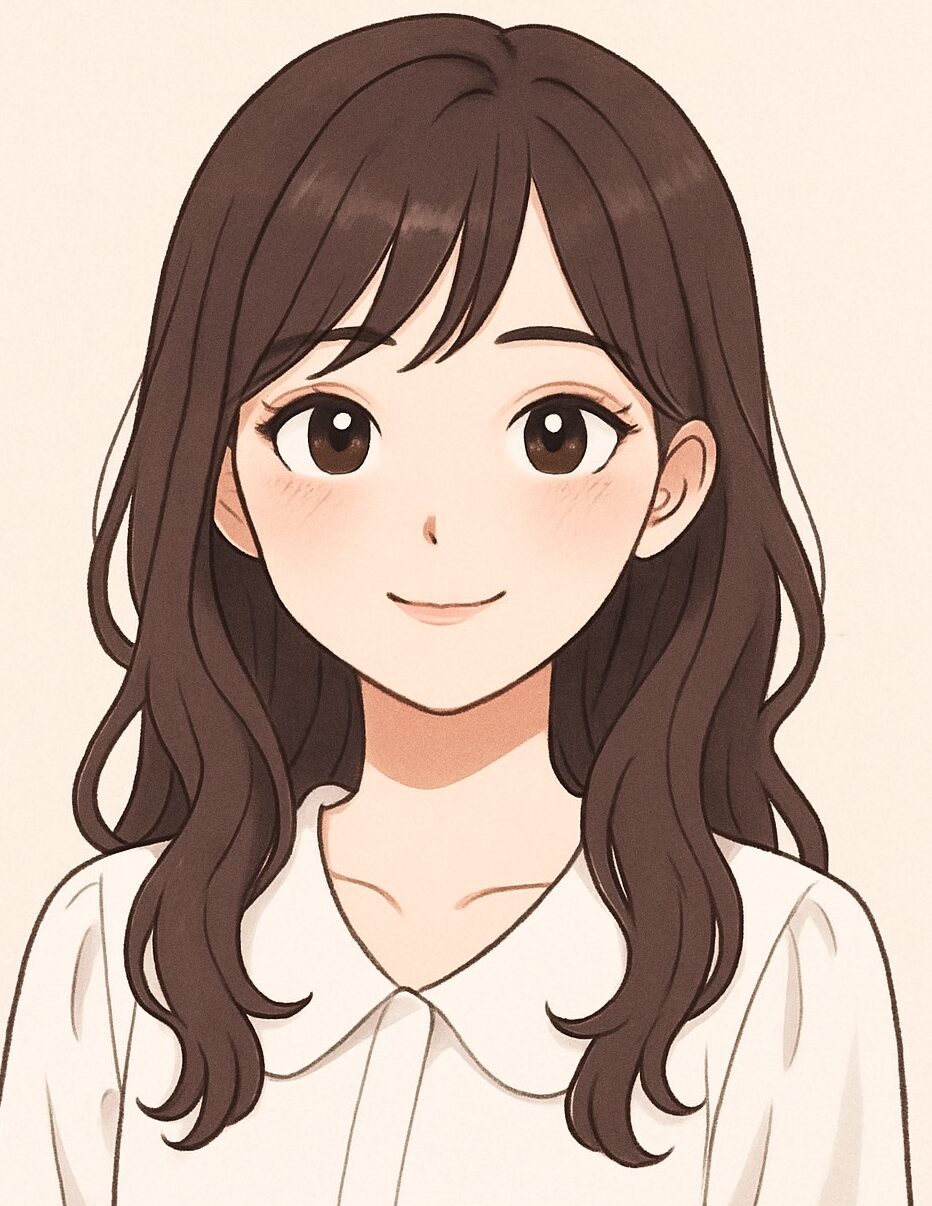
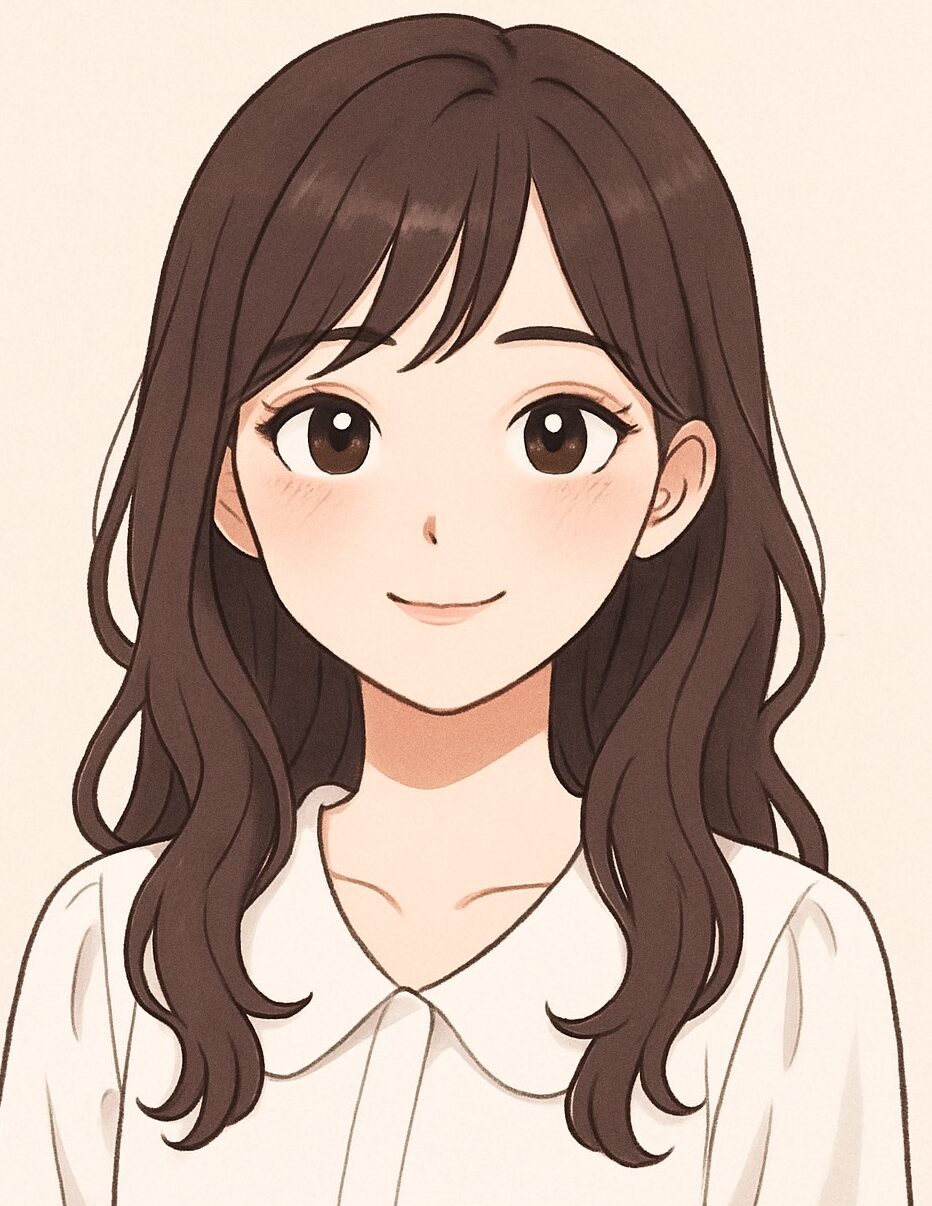
適度に手を抜くということができずにどんどん自分に負荷をかけてしまい産後鬱と診断されてしまうことになりました。
発達の速さに惑わされる日々
忘れもしない2021年8月22日、日曜日。
朝から暑くて、クーラーのきいたリビングで3人でごろごろしていたときのことです。
夫が先にお昼寝してしまい、私が声をかけながら過ごしていたその時、
ころん、と寝返りが成功。
そしてさらに驚いたのが、6ヶ月で「はじめの一歩」を踏み出したこと。
その後8ヶ月で靴を履き手を繋いで外を歩けるまでになりました。
周囲の赤ちゃんよりも明らかに運動発達が早く、
「すごい!」「優秀!」と思う反面、
「こんなに早いって、逆に大丈夫?」と不安もよぎりました。
後にわかったのは、高機能ASDでは“発達の速さ”が特徴のひとつということ。
当時はそんなことも知らず、ただただ戸惑っていました。
1歳半健診と初めての「様子見」診断
この頃には、「何かが違う」という違和感がどんどん膨らんでいました。
問診票の「気になることがある」に○をつけ、心理士さんの面談を希望。
しかし、結果は
「むしろ優秀ですね」
その言葉に安心したような、でもやっぱりモヤモヤするような、複雑な気持ち。
“優秀すぎて心配”という違和感は、誰にも理解されなかったのです。
今思えば、1歳半健診でフォローが入るのは「遅れがある子」。
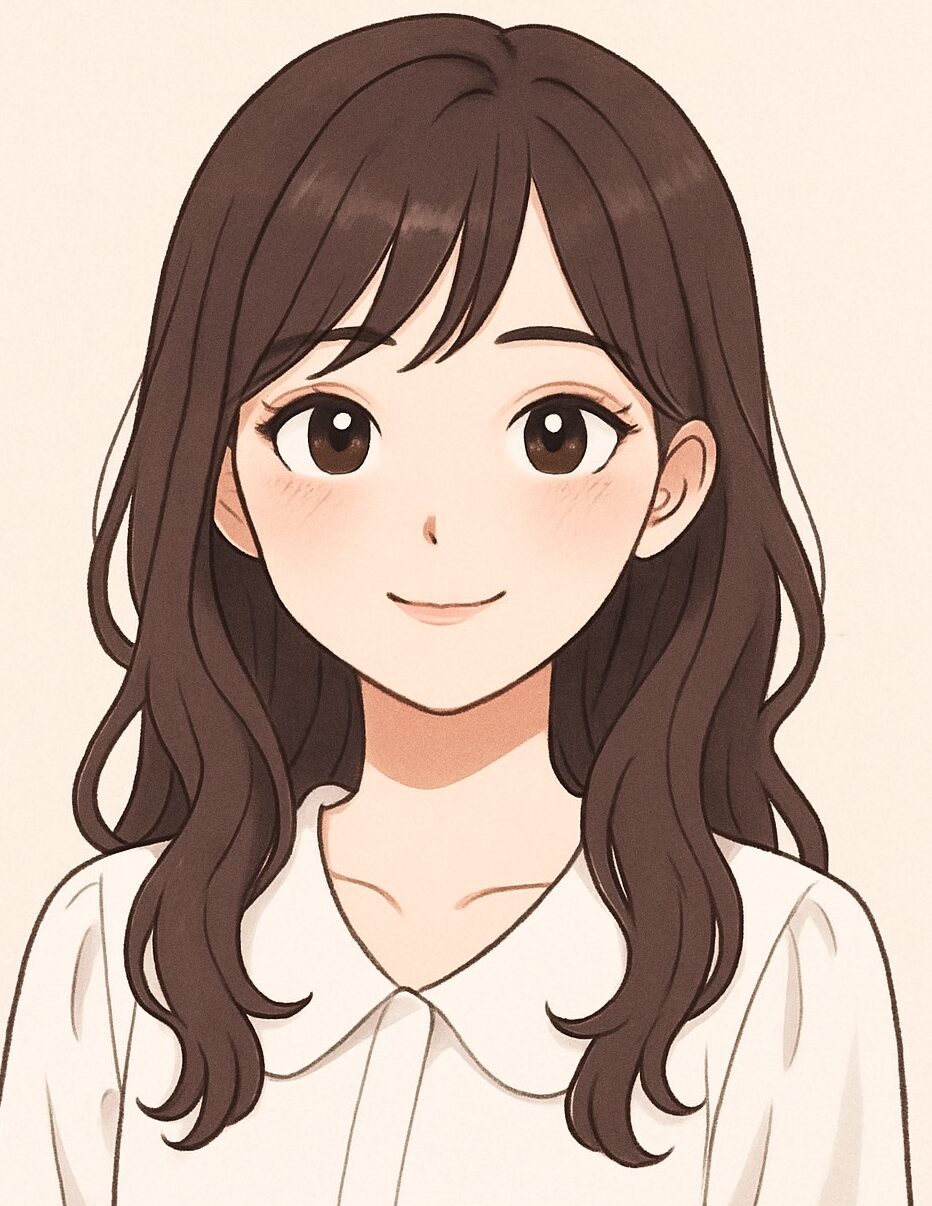
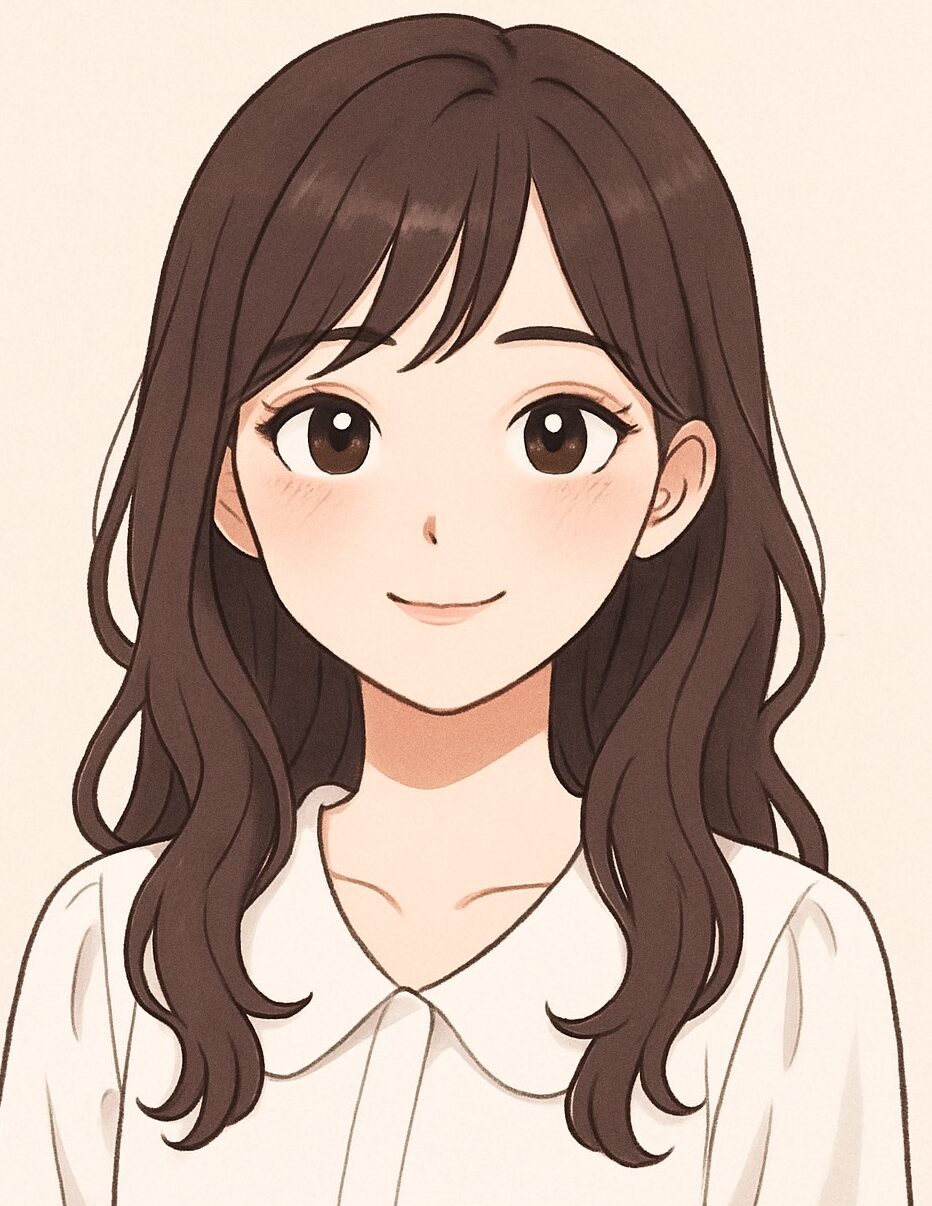
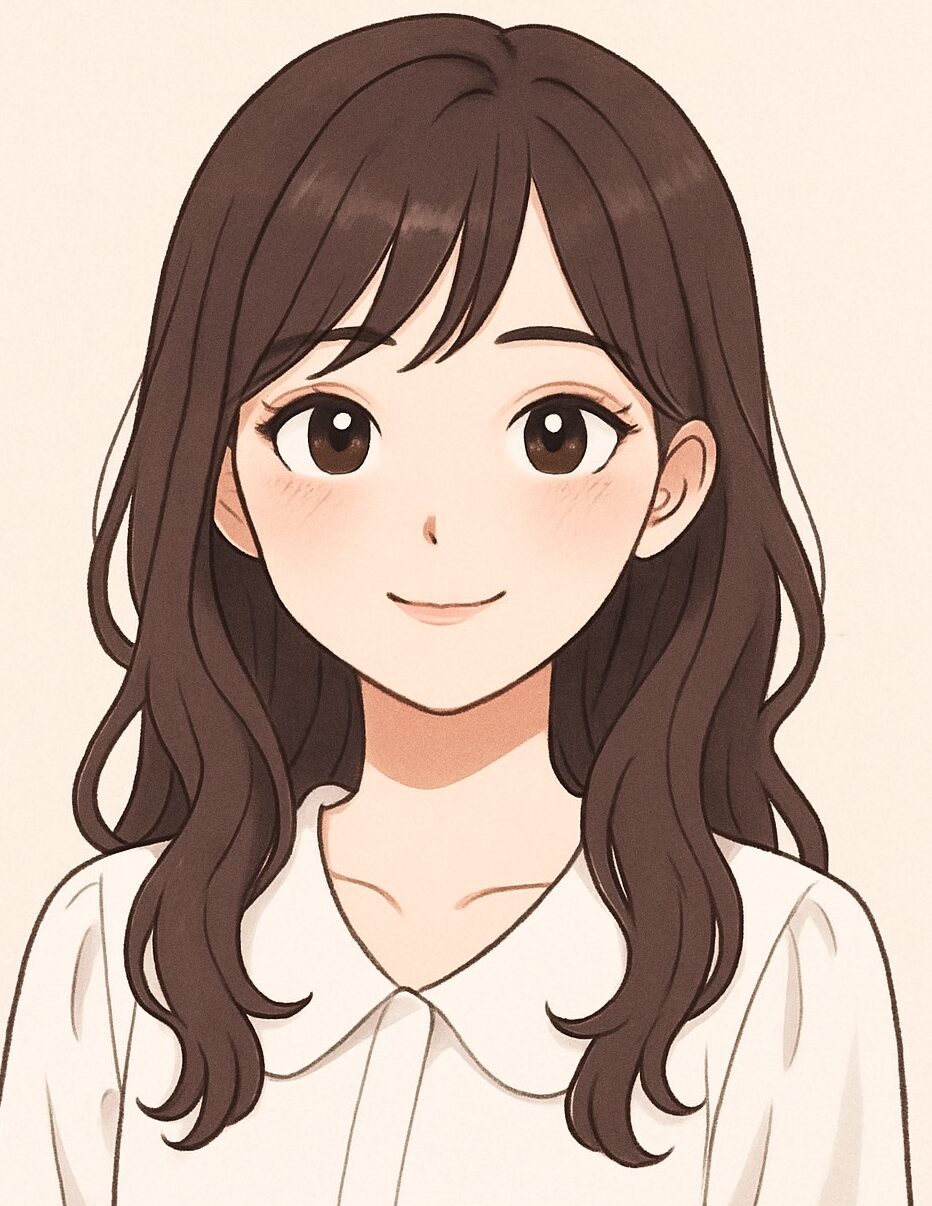
どうしても月齢が低いうちは発達が早すぎる子は見落とされやすいと感じています。
まとめ ― 当時の私が伝えたいこと
抱っこしかできなかった日々も、発達の速さに戸惑った日々も、
すべてが「息子のペース」だったんだと今なら思えます。
「他の子と違う」は怖い言葉じゃない。
それは“その子の特性が光っている証拠”。
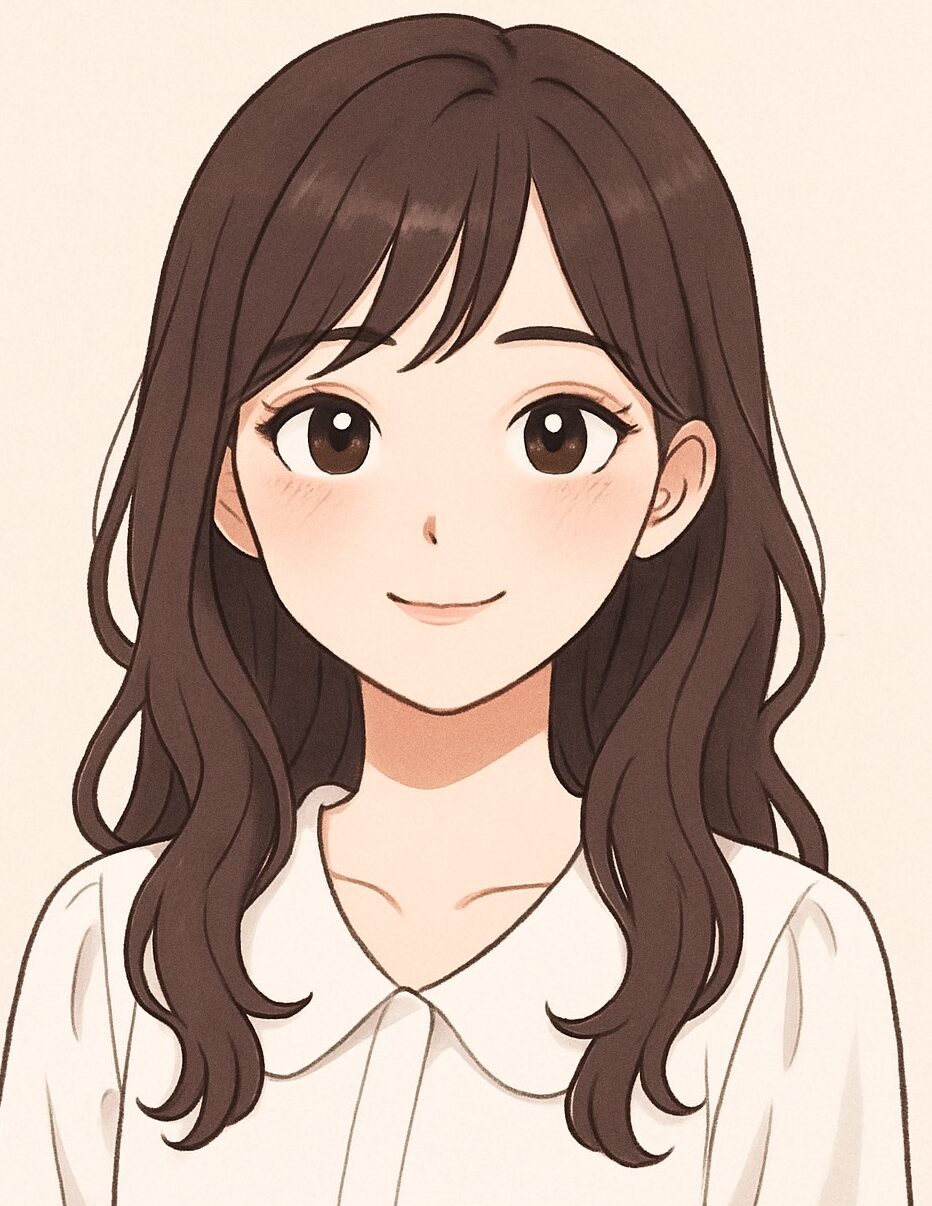
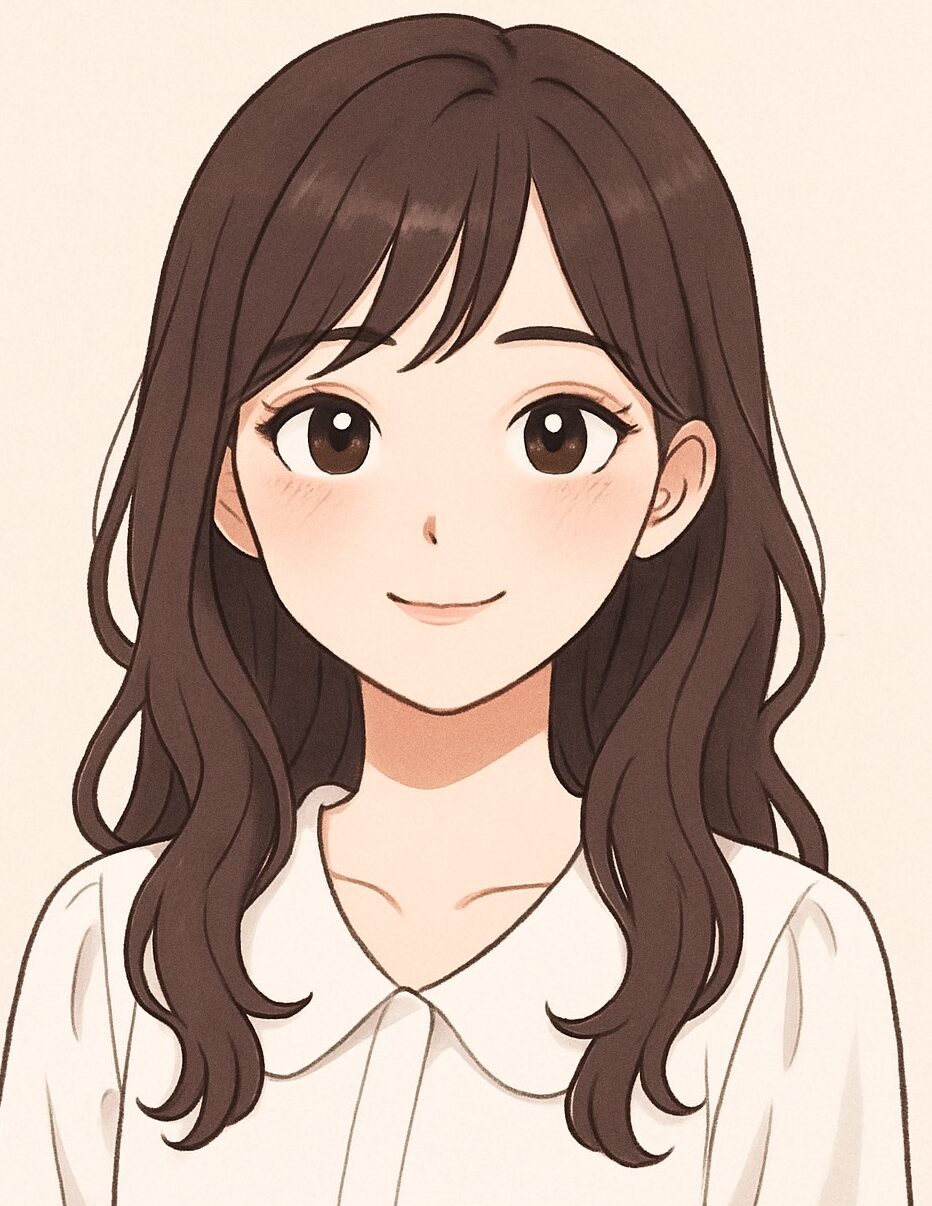
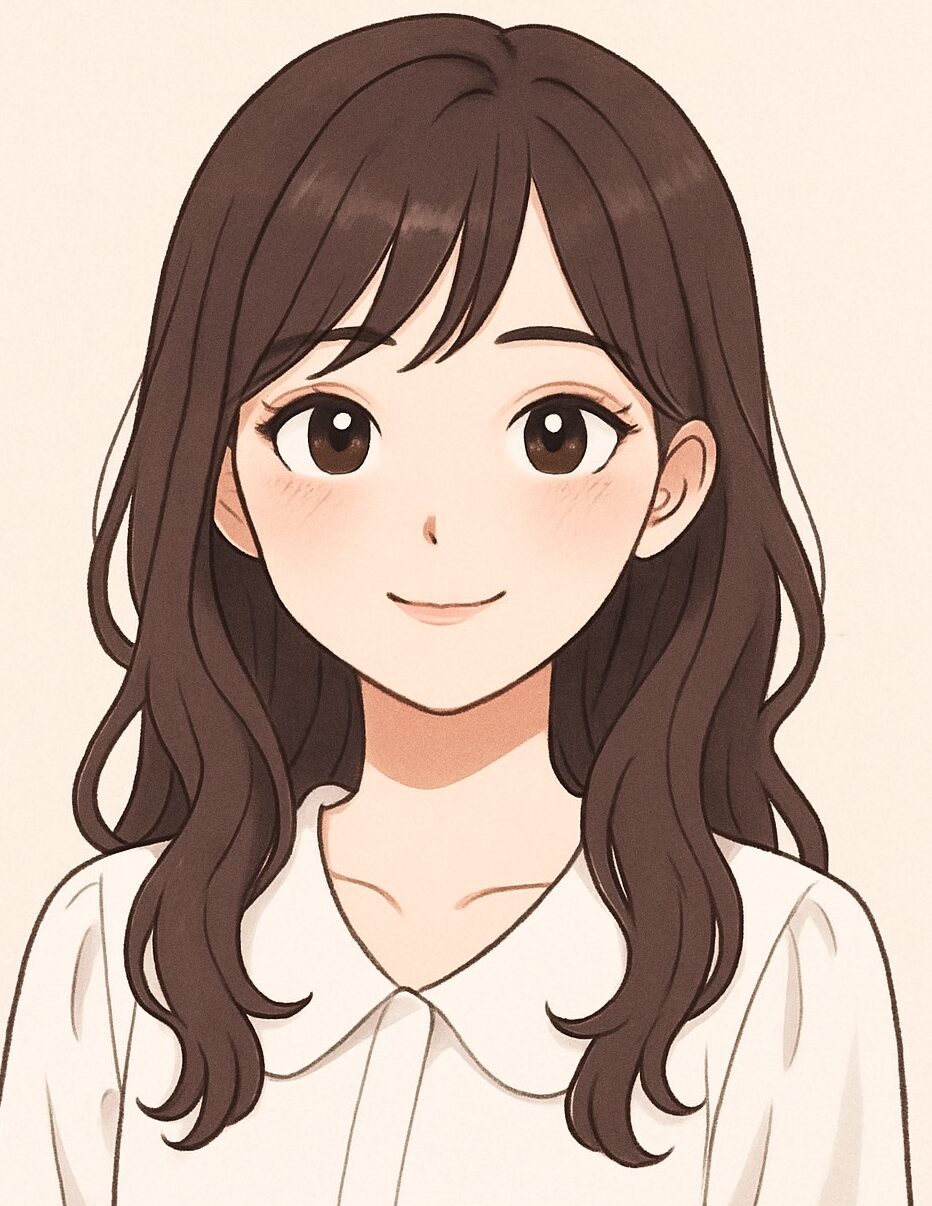
今振り返ると冷静にそう感じることができますが当時余裕がなかったのも紛れもない事実です。
次回は、そんな違和感を抱えながらも
少しずつ「親として動き出した」2歳前後の話を書いていきます。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d4bfd9c.e7f8bee2.4d4bfd9d.4f823153/?me_id=1380622&item_id=10000078&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkonnybaby%2Fcabinet%2Fsuperdeal_special%2Fimgrc0110172696.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント